・料理の科学
【目次】
(1) 料理の加熱
「料理」とは、食品や食材を調味料などと合わせて、加工することです。その加工には、「加熱」・「発酵」・「冷却」・「攪拌」など様々なものがありますが、多くの料理には、「加熱」が行われます。著書「The Omnivorous Mind(雑食の精神)」の中で、ジョン・S・アレンは、食品を火で熱することで、食品は軟らかくて食べやすくなり、消化・吸収がしやすくなり、同時によりクリスピーになると指摘しています。
食材を加熱することによって、食感が良くなったり風味が増したりと、料理がおいしくなるのはもちろんですが、加熱をすることによって、安全性を確保することもできます。自然界には、人体にとって毒である物質も多いです。加熱によって毒性をなくせば、食べられる食材もあります。また、食材は時間の経過に伴って、雑菌が繁殖することが避けられません。雑菌の中には、人体に有害なものもあります。あるいは、寄生虫が入り込んでいる食材もあります。しかし、加熱をすれば、雑菌や寄生虫は死滅するので、多くの場合、より安全に食べられるようになります。加熱の方法には、「焼く」・「炒める」・「揚げる」・「煮る」・「蒸す」の5つが考えられます。
(i) 焼く
「焼く」は、人類が火を発見したときから始められた、最も古い原始的な料理法です。たかだか1万年ほどの歴史しかない「煮る」や「蒸す」、油を使いこなすようになってから可能になった「炒める」や「揚げる」という料理法に比べて、「焼く」は桁外れに歴史が古いのです。人類が火を日常的に使用し始めたのが12万5千年ほど前と言われていますから、「焼く」はまさに料理法の王道なのです。
「焼く」は、「直火焼き」・「炭火焼き」・「鉄板焼き」・「炙り焼き」など、その焼き方は多岐に渡りますが、基本的には、炎などの熱源の放射熱や、空気を媒体としての熱の対流を利用して、食材を加熱する方法です。炎は触れれば火傷しますし、熱いのは分かりきっていることですが、私たちは直接炎に触れなくとも、炎の熱を肌で感じることができますよね。簡単に言えば、この温かさが「放射熱」と呼ばれるものであり、それは「遠赤外線」が原因です。遠赤外線は「電磁波」の一種であり、水分子などに運動エネルギーを与えることで、温度を上げる効果があります。炎からは遠赤外線が出ているので、離れていても温かく感じるのです。
ところで、この遠赤外線を上手く生かした料理法が、「炭火焼き」です。地球上のすべての物質は、「プランクの法則」より、多かれ少なかれ遠赤外線を放射していますが、木炭は、特に遠赤外線を多く放射する物質として知られており、その遠赤外線発生量は、なんとガス火のおよそ4倍とも言われています。「肉を焼くとなれば最上は炭で焼くこと」とはよく言いますが、これにはきちんとした科学的根拠があるのです。遠赤外線は電磁波なので、風などの空気の影響を受けません。また、加熱効率が非常に良いために、短時間で調理を済ませることができ、肉の脂やうま味を食材に閉じ込めることができるのです。さらに、そのような遠赤外線の効果だけではなく、炭火によって、肉の表面に「炭の香り」や「ミネラルを含んだ炭の灰」が付着することで、肉の味わいが増す効果もあるので、炭火で焼いた肉は特においしいのです。

図.1 「遠赤外線」を大量に放出する炭火
(ii) 炒める
「炒める」は、フライパンなどの加熱容器に少量の油を入れ、野菜や肉などの食材をかき混ぜながら加熱して、調理する料理法です。「焼く」との区別は曖昧ですが、「炒める」は、油を使ってかき混ぜながら加熱をするという違いがあります。「炒める」は、野菜炒め、炒飯、焼きそばなどで行われる一般的な料理法であり、その真髄は、「油を使いこなすこと」にあります。
油の比熱は水の1/2以下であり、わずかな熱でも、温度が上がりやすいのです。また、油が容器一面に広がることによって、加熱の温度を均一にでき、容器と食材の間に油膜ができることによって、食材と容器の付着を防ぐという役割も果たしています。さらには、油に脂溶性の香り分子を溶解させることで、食材に色々な香りを付けることもでき、具材に油膜が張ることによって、味にまろみや風味が出るのです。特に、油脂は食べ物の「コク」に関わっていることが知られ、香気成分を保持することで、食べ物に「コク」を付与する効果があります。一般に油分が含まれる食べ物がおいしいとされるのは、このためです。
通常は食材を炒めるときは、フライパンなどを十分に空焼きして、水分を飛ばしてから油を少量入れ、そのあとに食材を入れて炒めます。しかし、「テフロン製のフライパン」などは、空焼きをすると表面のコーティングが劣化する上、テフロンは油を弾いてしまい、表面に均一な油膜ができにくいので、本格的な炒め料理をするときは、やはり「鉄製のフライパン」に限ります。鉄製のフライパンは、油がよくなじんで表面に薄い油膜ができるので、食材に均一に熱が入るのです。
また、食材を炒めるときは、強火で短時間で調理するのが基本です。炒め料理は、短時間でも強火なので、しっかりと食材の内部まで熱が入っており、野菜などは、食感が生に近いシャキシャキの状態に仕上がります。
一般的に炒め料理といったら、やはり思いつくのは「中華料理」です。中華料理は、この「炒め」の技術が特に優れており、厚手の中華鍋などは、強火で食材を加熱するのに最適な構造です。中華鍋は、鉄製で重く分厚いため、熱容量が大きくなり、食材を加えても鍋の温度が下がりにくく、さらに底面が曲面になっているため、表面積が大きくなり、すべての食材に均一に熱を加えることができるのです。「中華料理は火加減が命」とはよく言ったものですが、中華鍋は、まさに中国人が叡智を尽くして作った調理器具なのですね。

図.2 中華鍋は、炒め料理に最適な構造である
(iii) 揚げる
「揚げる」は、100℃以上の高温に熱した多量の油の中で食材を加熱し、油の対流によって、熱を伝える料理法です。液体の対流による加熱であることが「煮る」に似ていますが、揚げ物に使用される油は、沸点が100℃を超えるので、水で「煮る」のとは異なり、短時間で高温の加熱調理ができます。このように、「揚げる」と「煮る」の最大の違いは「液体の温度」であり、たとえ油で揚げていても、100℃以下の温度で調理する場合は、「揚げる」とは言いません。
また、油は熱を伝える役目だけでなく、食材に吸収されて、栄養価や風味を高める働きもします。揚げ物の種類や揚げる条件によって異なりますが、揚げ物には大体その重量の10〜40%程度の揚げ油が含まれています。したがって、揚げ油の品質は、揚げ物の風味に大きな影響を持つといえるでしょう。
揚げ物は、通常150〜190℃という高温で調理し、材料の水分を急速に蒸発させ、表面を熱変性させ硬化させます。よく天ぷらなどをすると、調理時にブクブクと食材から泡が出ますが、あれは食材の水分が蒸発して生じた水蒸気です。揚げ物は、このように表面の水分を失って硬化することで、表面がサクサクとした食感になるのです。
また、天ぷらの変わり種として、アイスクリームの天ぷらがありますが、これは「揚げる」が短時間で終わる調理法だから可能なことです。高温かつ短時間こそが、揚げ物の加熱の最大の特色なのです。

図.3 天ぷらは、油の沸点の高さを利用している
(iv) 煮る
「煮る」は、水を媒体にして熱の対流を利用する料理法であり、最大の利点は、温度管理をしやすいということです。水は圧力鍋などを使わない限り、100℃までしか温度が上がりません。それ以上の加熱をしても、水蒸気になるだけです。したがって、水がある限り、食材の温度は100℃を超えないので、食材は焦げることがなく、長い時間加熱をすることができるのです。
さらに、水を媒体にした加熱料理は、「溶媒」としての水の性質に着目する必要があります。溶媒としての水は、食材中の水溶性の成分を溶解させたり、食品に味を付けるための調味料の運搬役となったり、大きな比熱を生かして食材を保温したりと、様々な働きをします。
人類が「煮る」という料理法を始めたのは、1万年ほど前に土器を発明してからだといわれていますが、人類はこれから、ほとんど何でも食べられるようになりました。それまでは、ある種の野草などは、苦味や渋味があるため食べることができませんでした。しかし、野草をわら灰や木炭を溶いた「アルカリ性の水」で煮ることで、灰汁が抜けて、おいしく食べられるようになったのです。この理由は、灰汁の原因となる「有機酸塩」や「アルカロイド」が、煮ることで水に溶け出てしまうからです。野山に生える植物をよく食べた縄文人も、このように土器で灰汁抜きをすることで、生活が可能になったのです。

図.4 煮物は、温度管理がしやすい
「灰汁抜き」は、本来えぐみを取るなど、食味の問題から行っていたことですが、灰汁抜きにより、有害物質が除去されるときがあります。例えば、ワラビに含まれる「プタキロサイド」は、動物実験で100%発ガンしますが、この物質は、灰汁抜きの操作でほとんどが分解され、また、残ったものも茹で汁に移行するので、安全に食べられるようになるのです。フキに含まれる肝毒性を現す「ピロリチジン系アルカロイド」や、タケノコに含まれる「青酸配糖体」なども、灰汁抜きの操作によって除かれることが分かっています。
さらに、灰汁抜きで除かれる化合物の中には、「シュウ酸」や「シュウ酸塩」もあります。サトイモ科には有毒植物が多く、その1つであるクワズイモは、「シュウ酸カルシウム」の結晶を大量に含んでおり、これを口にすると、口の中に水疱ができたり、舌や咽頭に浮腫が生じたり、唾液の分泌亢進が起きたりして、しゃべるのが困難になるような症状が24〜48時間続きます。そして、舌の浮腫が酷ければ、呼吸困難に陥ることもあるといいます。その他のサトイモ科の植物(カラスビシャクやミズバショウ、ザゼンソウなど)にも、シュウ酸カルシウムの結晶を大量に含むものがあります。
一方で、サトイモ科以外の植物では、タデ科のオオイタドリやスイバなどに、「シュウ酸水素ナトリウム」などの水溶性シュウ酸塩が大量に含まれています。そのため、スイバの野菜スープを大量に摂取し、嘔吐や下痢、意識障害をきたし、死亡した例があります。これは、水溶性のシュウ酸水素ナトリウムNaHC2O4が、血液中のカルシウムイオンCa2+と結合し、不溶性のシュウ酸カルシウムCaC2O4を生成するために起こる中毒です。
NaHC2O4 + Ca2+ → CaC2O4 + Na+ + H+
この中毒の際の剖検によれば、腎皮質や肝臓の毛細血管、肺、心臓にシュウ酸カルシウムの結晶が認められたといいます。これは、大量の水溶性シュウ酸塩の摂取によって、低カルシウム血症となり、さらに、臓器内でシュウ酸カルシウムの結晶が沈着して、障害を引き起こしたものと考えられています。
(v) 蒸す
「蒸す」は、水を加熱して発生した水蒸気の対流を利用して、食材を加熱する料理法です。水蒸気自体は、加熱をすれば100℃以上になります。しかし、蒸し料理は、水蒸気の熱が食材に奪われていく過程で加熱をする調理法なので、食材の温度は100℃以上にならずに、ゆっくりと加熱をすることができます。そのため、蒸し料理の仕上がりは、ふっくらしっとりとするのです。
同じ水の対流を利用することは、「煮る」と似ています。しかし、その違いは、「蒸す」が気体の対流を利用することです。したがって、「煮る」ことによって生じる、うま味や栄養の流失が、極めて少ないのです。さらに、液体の中では、水の物理的な動きによって、食材は煮崩れしてしまうことがありますが、「蒸す」では、その型崩れが起きることがなく、綺麗な状態で仕上げることができます。つまり、蒸し料理は、持ち味をそのまま活かす料理に最適なのです。
蒸し料理に向いているのは、大型で適度な水分を含み、焦がさずに長時間加熱したいものです。こういう条件にピッタリなのが、サツマイモやトウモロコシなどの、デンプンを多く含む食材です。シュウマイや饅頭のように、小麦粉をこねて固めた料理も適しています。ただし、食材中の水分が少ないと、凝縮した水が吸収され、逆に食材中の水分が多いと、水分が流れ出すことがあるので、注意が必要です。
一昔前の日本では、どの家庭にも「蒸籠(せいろ)」などの蒸し器があったものです。茶碗蒸しや赤飯などの蒸し料理は、家庭料理の代表だったのです。今では、電子レンジが蒸し器のような働きもできるので、その座に取って代わっていますが、やはり電子レンジよりも、本物の蒸し器で作った蒸し料理の方が、格別においしく感じます。

図.5 蒸籠で蒸し料理を作る
なお、電子レンジは、「マグネトロン」という装置で発生させた「マイクロ波」を食品に吸収させ、食品自体を発熱させて加熱する調理器具です。電子レンジの原理は、アメリカの大手軍需製品メーカーの「レイセオン社」で働いていたパーシー・スペンサーによって、偶然に発見されました。スペンサーは、軍事レーダーの研究をしていたのですが、マイクロ波によって、ポケットの中のチョコバーが融けていたことを発見しました。ここからレイセオン社は、マイクロ波による調理について1945年に特許を取り、1947年に最初の製品を発売しました。しかしながら、実はこれ以前から、マイクロ波が物質を加熱する現象は報告されていました。例えば、第二次世界大戦中に日本海軍のレーダー開発実験を行っていた研究所では、レーダーの研究装置の近くにサツマイモを置いておき、実験終了後にはそれが焼き芋になっていたため、これを食べるのが楽しみだったといった話があります。
マイクロ波は、「エネルギー源としては使えない」と常識的に考えられていましたが、セレンディピティのもとで発見した現象を、製品化まで押し上げたのがスペーサーで、私たちが電子レンジを使えるのは、この行動力の賜物です。現在、日本で電子レンジで使われているマイクロ波は、周波数が2,450 MHzの電磁波です。2,450 MHzとは、波が1秒間に24億5千万回振動するということです。電子レンジの原理は、1秒間に24億5千万回という速い回数でもって、食品に「交番電場」をかけることにあります。電場が逆転する度、食品中の水分子は、電場の方向に沿う並び方に向きを変えます。向きを変える度に、水分子同士の摩擦熱を生じ、この熱によって、食品を加熱するのです。
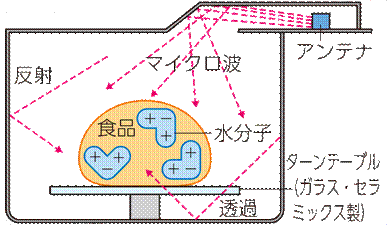
図.6 電子レンジの原理は、軍事研究の際に偶然発見された
(2) 肉のおいしさとメイラード反応
焼いた肉は、なぜおいしいのでしょうか?肉を食べるときに、焼かずに生で食べるという人は、まずいないでしょう。「タルタルステーキ」のように、生食を楽しむ食べ方もありますが、肉は焼いて食べるのが一般的です。肉を焼く理由は、焼いて食べることで、「食中毒」などのリスクを減らすことができますし、何よりも「おいしくなる」からです。人類は、大昔から狩猟によって動物を捕らえ、その肉を食べてきました。人類が火を発見する以前は、動物の肉は、生で食べられていたのです。生で食べるなんて今では信じられませんが、それでも動物の肉はおいしいので、生の状態でも食べられていたのです。

図.7 肉は生食よりも、火を通した方がおいしい
動物は死ぬと、直ちに「死後硬直」を起こします。その理由は、呼吸による筋肉への酸素供給が止まって、細胞の「好気的な代謝」は停止しても、「嫌気的な代謝」は継続して行われるからです。すなわち、動物は死んでも、細胞では嫌気的な「解糖系」による代謝が続くのです。これにより、筋肉中のグリコーゲンは嫌気的に代謝され、「乳酸」になっていきます。乳酸濃度が大きくなっていくと、筋肉中のpHは低下していき、筋肉のタンパク質が変性して、硬い状態になります。この状態が、いわゆる「死後硬直」です。この状態では、肉は硬くて風味が乏しいです。
しかし、死後硬直からしばらく経って、筋肉は最大硬直を過ぎると、微生物やタンパク質分解酵素などの作用で、筋肉の「自己消化」が始まります。この現象によって、筋肉は徐々に軟らかくなり、タンパク質やATPが分解され、「グルタミン酸」や「イノシン酸」などのうま味物質が生成します。特にグルタミン酸は、食品中のアミノ酸の中で最も多く含まれる成分であり、肉や魚などのタンパク質を構成しているアミノ酸の約15%を占めています。食肉分野では、自己消化によってうま味を増やす方法を「熟成」と呼んでいます。長いものでは、「乾燥熟成肉(ドライエイジング)」などの方法によって、室温を1〜3℃、湿度を60〜80%に保ち、4〜8週間も熟成させることがあります。
「乾燥熟成」は、温度が高すぎれば肉は腐ってしまうし、低すぎれば肉が凍ってしまい、熟成ではなくなってしまいます。基本的に雑菌は、肉の表面にしかいません。雑菌は水分がないと繁殖できないので、表面を乾燥させることで、有害な雑菌の繁殖を抑制することができるのです。温度と環境などのメンテナンスに相当な手間がかかりますが、熟成が進んでいくと、味や香りが濃厚なものに変わっていきます。乾燥熟成が進んだ状態では、肉の外観は赤黒く変色し、薄く白カビなどが発生する場合もありますが、それが乾燥熟成で最高の状態ともいわれています。乾燥熟成は、ごく一部の高品質な牛肉に対してのみ行われ、鮮度の落ちが早い鶏肉や、熟成期間の短い豚肉などでは、ほとんど行われていません。

図.8 「乾燥熟成」させることで、酵素などの働きで肉のタンパク質や核酸が分解され、うま味が増すとともに肉が軟らかくなる
しかし、熟成が進んでうま味が増したといっても、肉はそのままでは、筋繊維が「コラーゲン」の強靭な結合組織で囲まれていて、硬くて食べにくいです。コラーゲンは、加熱すると収縮し、さらに加熱するとコラーゲン間の結合が切れ、「ゼラチン化」が起こります。このようにすると、結合組織の強靭な結合は弱くなり、筋繊維がほぐれて、肉は軟らかくなるのです。焼いた肉が軟らかく、噛み切りやすいのはこのためです。けれども、肉は加熱とともに、筋繊維のタンパク質の変性が始まるので、加熱しすぎると、肉が硬くなっていきます。ステーキなどでは、「レア」・「ミディアム」・「ウェルダン」など、様々な焼き方がありますが、加熱中の肉の硬さは、この「筋繊維の硬化」と、「コラーゲンのゼラチン化」の進行の兼ね合いで決定されるのです。
表.1 ステーキの焼き方と内部温度
|
焼き方 |
内部温度 |
特 徴 |
|
レア |
55〜65℃以下 |
表面は焼けているが、中は「生」の状態。中は「鮮紅色」で肉汁が多い。 |
|
ミディアム・レア |
約65℃ |
「レア」よりは火が通っているが、肉の中心部はまだ「生」の状態。切ると赤い肉汁がうっすらとにじみ出る。 |
|
ミディアム |
65〜70℃ |
中心部はちょうどよい状態に火が通っており、薄いピンク色。切ると肉汁が少ししか出ない。 |
|
ウェルダン |
70〜80℃ |
表面も中も充分に火が通り、褐色で灰色がかっている。肉汁は少ない。 |
肉は焼くことによって、肉の脂が融解してとろみが増し、食感が良くなっておいしくなります。しかし、実はこの「焼く」という過程には、肉をおいしくするもう1つの秘密が隠されているのです。肉を鉄板などで焼くと、肉の表面がカリカリに焼けて、食欲をそそる香ばしい匂いを発するようになります。これは、肉の表面で「メイラード反応」という化学反応が進行しているからです。
「メイラード反応」とは、「アミノ化物」と「還元糖」の混合物を150℃以上の温度で加熱したときなどに見られる、「褐色の重合体」を生成する非酵素的褐変反応のことです。「メイラード」とは、この反応を初めて発見したフランスの化学者であるルイ・カミーユ・メイラードの名に由来するものです。大抵の食品には糖とアミノ酸が存在するため、加熱食品では必ず起こる反応です。このとき生成する褐色物質は「メラノイジン」とも呼ばれ、様々な高分子化合物の混合物です。その化学構造はあまり詳しく分かっていませんが、各種の複素芳香環(窒素や酸素などを含む芳香環)を含む、複雑な重合体であると推測されています。肉を焼いたときに、表面が褐色になるのは誰でも知っていることだと思いますが、あれは単なる「焦げ」ではないのです。あの「焦げ」のようにも見える褐色物質こそ、肉をおいしくしている物質の正体なのです。
メイラード反応は、グルコースやフルクトースなどの還元糖のアルデヒド基(-CHO)に、アミノ酸やタンパク質などのアミノ化物のアミノ基(-NH2)が求核攻撃して、「シッフ塩基」と呼ばれる化合物を作る反応から始まります。そして、数段階の反応および副反応を経て、様々な「褐色物質」を生成していきます。このようにして生成した「褐色物質」は、特有の香気を持ち、肉が焼けるときの香ばしい匂いは、この褐色物質の匂いであるといわれています。また、この褐色物質は反応性が高いので、抗酸化作用を持ち、表面を焼いた肉は、生肉と比べて腐敗しにくくなります。焼いた肉の代表的な香気成分としては、「ビス-2-メチル-3-フリルジスルフィド」があります。この化合物は、食品工業で「焼いた肉の香り」を付けるのに使用されています。
アミノ化物(タンパク質・ペプチド・アミノ酸など) + 還元糖(グルコース・フルクトース・マルトースなど) → 褐色物質(メラノイジン)
このようなメイラード反応は、他の食品にも多く見られ、食品工業においては、製品の着色香気成分の生成や、抗酸化性成分の生成などに関わる、重要な反応とされています。例えば、タマネギを弱火でじっくりと炒めると、飴色になって香ばしい匂いがしますが、あれはメイラード反応が進行しているからです。他には、コーヒー豆の焙煎や麦茶、チョコレート、味噌、醤油などの色素形成、デミグラスソースの褐変、パンやご飯のお焦げの形成など、身近には意外とメイラード反応を利用した食品が多いです。
なお、メイラード反応において大切なことは、この反応は150℃以上の高温でしか起こらないということです。つまり、煮たり蒸したりといった料理では、メイラード反応を起こすことができないのです。焼く料理では、食材に焼き跡が付き、これが視覚的に食欲をそそる効果も大きいのですが、この焼き跡もメラノイジンに由来します。このような理由から、積極的にメラノイジンを作るため、みりんと醤油を混ぜたタレを使う「照り焼き」という調理法があります。また、焼くことによって、食材からの水分が減少するのも利点と考えられます。すなわち、煮るよりも焼いた方が、水分の減少が大きいので、味の成分が濃厚になって、おいしくなるのです。

図.9 「照り焼き」では、タレの糖分により食材の表面が艶を帯び、「照り」が出るのが名前の由来
また、このメイラード反応と似たような反応に、牛乳や砂糖などを煮詰めて進行させる、「カラメル化反応」があります。しかし、これはメイラード反応とは、全く異なる反応です。カラメル化反応は、「糖類」だけを煮詰めて褐色の重合体を作る反応であるのに対して、メイラード反応は、「糖類」の他に「アミノ化物」も反応に必要だからです。また、カラメル化反応は、メイラード反応よりもはるかに低温で起こるという違いもあります。ちなみに、糖類の代表格である「砂糖」は還元糖ではないので、アミノ化物と反応させても、メイラード反応は進行しません。しかしながら、カラメル化反応で生成するカラメルも、メイラード反応の褐色物質ほどではないものの、抗酸化作用を持つため、食品工業では同じく重要な反応の1つとなっています。

図.10 カラメルは、「カラメル化反応」によって糖類から作られる
メイラード反応は、「着色」・「香気」・「抗酸化作用」の働きがあるため、料理をおいしくするためには、必要不可欠な反応です。しかし、料理がおいしくなるからといって、あまりにも加熱し過ぎれば、当然真っ黒に「焦げ」てしまいます。メイラード反応を知らない人にとっては、「褐色物質」も「焦げ」も同じ物質のように思えるかもしれませんが、生成は全く別の反応機構なのです。「焦げ」を生成する反応は、「炭化反応」と呼ばれるもので、酸素を遮断した状態で有機物を加熱すると分解が生じ、揮発性の低い炭素だけが残る反応なのです。
つまり、加熱中に酸素の供給が不十分であると、「焦げ」ができてしまうのです。フライパンなどで肉を焼いているとき、うっかり放置して焦がしてしまった経験はありませんか?このような炭化反応を進行させないようにするためには、肉を適度にひっくり返したり、かき混ぜたりして、食材に十分な量の酸素を供給して、温度を上げ過ぎない必要があるのです。食材を加熱するときにひっくり返したりするのは、食材に熱を満遍なく伝えるためでもありますが、炭化反応の進行を阻害して、効率よくメイラード反応を進行させるためでもあるのです。

図.11 「焦げ」には、「ヘテロサイクリックアミン」などの発ガン性物質が含まれる
「焦げ」は、栄養分が消失していて苦味を持ち、さらには「ヘテロサイクリックアミン」などの発ガン性物質が含まれています。ヘテロサイクリックアミンは、肉や魚に含まれる「トリプトファン」や「チロシン」などのアミノ酸に熱が加えられると生成します。「焦げ」に含まれる発ガン性物質の濃度は、微量だとも言われていますが、それ以前に「焦げ」はおいしくないですし、あまり進んで食べたいものではありません。理論上は、酸素の供給が十分なら、いくら強火で加熱しても、炭化反応は進みません。しかし、タマネギなどの焦げやすい食材を、焦がさずに強火で調理するのは、不可能に近いです。メイラード反応を選択的に進めるためには、弱火でじっくりと加熱するのが一番良いのです。
ところで、ヘテロサイクリックアミンの作用は、食事内容によっては、抑制されることが知られています。例えば、野菜の食物繊維などは、一部のヘテロサイクリックアミンを吸着し、それを除去することが知られています。また、焼き魚や焼肉で見られるヘテロサイクリックアミンの量が、大根おろしによって低下するという現象も認められています。これらの解毒機構の詳細については、未だ不明の点も多いです。しかし、私たちの食卓で、焼き魚や焼肉に大根おろしが付けられることが多いのは、大変好ましいことであり、今後も生活の知恵として、続けていきたい食習慣です。

図.12 大根おろしには、焼き魚に含まれるヘテロサイクリックアミンの量を低下させる作用がある
(3) 魚の刺身のおいしさ
新鮮な動物や魚の肉を切り取って生で食べることは、人類史の初期の段階で行われてきたことです。しかし、人類が火を使いこなすようになってからは、「生食」の習慣は次第に廃れていき、加熱などの調理をしてから肉を食べるようになりました。それは、食中毒などのリスクを考えれば、当然のことかもしれません。加熱をすることで、動物や魚の肉は、ある程度の期間は保存ができるようになったのですから。
しかしながら、日本は四方を海で囲まれ、新鮮な魚介類をいつでも手に入れられるという恵まれた環境があったために、魚介類を生で食べる習慣が残りました。これは、世界的に見ても、珍しい習慣です。現在では、寿司や刺身などの「日本料理」は、世界的に楽しまれている料理ですが、以前は「魚を生で食べるなんて・・・」というような、悪いイメージが少なからずあったのです。
日本人は、古くから魚を生で食べることを、重要な文化として伝えてきました。これは、日本料理では「割主烹従」と呼ばれるもので、素材に手をあまり加えず、素材そのものの風味や良さを引き立たせるという調理法が、尊重されていたからです。「割主烹従」の「割」とは切ること、「烹」とは煮たり焼いたりすることという意味です。すなわち、「割主烹従」とは、「食材を切って生で食べること」を主とし、「煮たり焼いたりして食べること」を従とするものなのです。日本料理は、このように食材を切ることを非常に重視しており、食材を切ることのみでおいしくするのが、日本料理の真髄なのです。
特に「刺身」などは、食材を切ることのみで調理を終わらせる料理であり、古くから日本人に親しまれてきました。出刃や柳刃といった和包丁は、世界的に見ても他に例を見ない片刃のナイフです。慣れていなければ、真っすぐ切ることさえ難しいといわれています。しかし、片刃の包丁は、両刃の包丁と比べて、刃の食い込みがよく、切れ味が良いとされています。細胞組織を真っすぐ切断することで、切断面の表面積は最小となり、酸化されにくくなるのです。刺身の切り口は、「角が立っていること」が重要とされるのは、これが理由です。

図.13 角が立った「刺身」が美味とされる
新鮮な魚が生食に向いているのにも、科学的な理由があります。「魚肉」と「畜肉類」では、その食べ方に大きな違いがあります。「畜肉類」は、強固なコラーゲンに囲まれた筋繊維を持つため、死後硬直中は硬くてうま味も少なく、しかも「ドリップ(にじみ出てくる水分)」が多くて、とても食べられたものではありません。ところが、死後硬直が過ぎてからは、先にも説明したように、「自己消化」による肉の熟成が始まり、うま味成分が増加して、おいしくなるのです。しかし、畜肉類は熟成した肉でも、生でそのまま食べるということはあまりしません。「馬刺し」などの例外はあるものの、畜肉は焼いて食べるのが一般的なのです。
それに対して「魚肉」は、コラーゲンの少ない軟らかな筋肉からなるので、熟成を待たなくても、すぐに食べることができます。これがまさに魚の「刺身」であり、刺身という料理は、「死後硬直中の魚肉」を食べているのです。魚の刺身は、より新鮮なものが好まれますが、これは新鮮なものほど死後硬直が顕著で、食感が良いとされるからです。ちなみに、同じ刺身でも、馬刺しなどの畜肉類の刺身は、ある程度の熟成はさせています。これが、畜肉類と魚肉の刺身の違いですね。
とはいえ、魚の刺身は、新鮮ならば何でも良いという訳ではなく、例えば魚を「活けしめ」にしておくと、数時間経って、うま味がぐっと増します。これは、やはり熟成が進んで、うま味成分である「グルタミン酸」や「イノシン酸」ができてくるからです。これは、魚をどう食べるかにもよりますが、例えば、マグロや大型のヒラメなど、畜肉類のように2〜3日熟成させてから食べるほうが良いとされる魚もいます。
また、同じ魚でも、関西地域では、「うま味」よりも「食感」を重視するため、活けしめ後、なるべく早く食べる傾向があります。これは「活造り」と呼ばれる料理で、宴会などではしばしば見られます。ときに、肉は骨から切り取られているのに、口の辺りがピクピクと動いていることも珍しくありません。これは、海水や醤油などに含まれる塩分が、筋肉に作用して、筋肉が収縮するためです。刺身になった魚が、まだ生きている訳ではありませんが、魚が新鮮な証拠です。一方で、関東地域では、肉質は軟らかくなりますが、しばらく熟成させてうまみ成分を増加させ、「食感」よりも「うま味」の方を重視する傾向にあります。

図.14 新鮮なアジの「活造り」
(4) 料理を「おいしい」と感じるのはなぜか?
アメリカの心理学者のアブラハム・マズローは、人間が生命を維持するための基本的な欲求として、睡眠欲・食欲・排泄欲を「生理的欲求」としました。極端なまでに生活上のあらゆるものを失った人間は、この生理的欲求が他のどの欲求よりも、最も主要な動機付けになることが知られています。これらの欲求は、まず何よりも優先される本能の欲求であり、脳の「報酬系」と呼ばれる神経系と、非常に密接な関わりがあります。つまり、これらの欲求が満たされたとき、私たちは喜びや幸せを感じるように作られているのです。

図.15 「マズローの欲求段階説」では、人間の欲求を5段階の階層で理論化している
私たちは食物を口にするとき、「味覚」・「嗅覚」・「触覚」・「視覚」・「聴覚」の五感すべてを通じて、食物を認識します。その五感を通じて得られる喜びや幸せこそが「おいしさ」であり、食物をおいしく食べるということは、生理的欲求を満たし、喜びや幸せを感じるということです。五感のうちで、「味覚」および「嗅覚」は、「化学物質」を介して感じる感覚です。味覚の基本構成要素は、かつて言語や食習慣を背景に、欧米で支持されてきた「甘味」・「塩味」・「酸味」・「苦味」の4基本味に、日本古来の出汁に見出された「うま味」を加えた5基本味が、現在では国際的にも受け入れられています(おいしさの科学を参照)。
一般的に、私たちは「欠乏している栄養素」などを摂取したとき、つまり、「生理的欲求を満たす食物」を食べたとき、「おいしい」と感じるようにできています。逆に「生理的に有害な物質」、例えば「毒」などに対しては、苦味などの情報から、「まずい」と感じます。これは、「アルカロイド」などの毒物が苦味を持つことが多いため、「苦味=毒」と本能的に感じているからだと思われます。苦いものを生後間もない乳児に与えると、乳児は口を「への字」に曲げて、泣き出します。持って生まれた本能が、「苦いもの」を避けさせるのです。単細胞生物である大腸菌や粘菌に「苦いもの」を与えても、それを避けるような行動を取ります。このように、食物を口にしたときに感じる「本能的な感覚」こそが、「おいしさ」を決定する大きな要因であり、人間が食物を口にしたときに味覚から得られる情報は、一般的に次のように整理することができます。
ヒトの場合、味覚の中で最も敏感に感ずるのが苦味、次いで酸味、塩味、うま味です。そして、一番感度の低いのが甘味ということになっています。苦味は毒などの有害物質の情報を伝える味、酸味は腐敗したものの情報を伝える味であり、わずかな濃度でも敏感に感ずることで、私たちの安全を守ることになります。最も感度の低い甘味は、私たちのエネルギー源であるグルコールなどの味です。必要なエネルギーをできるだけたくさん確実に確保するための情報で、比較的緊急性が低いため、感度が低くなっていると考えられます。
表.2 「味覚」から得られる情報
|
基本味 |
代表的な物質 |
得られる情報 |
舌の感度 |
シグナル |
|
甘味 |
スクロース、グルコース |
糖の存在 |
低い |
嗜好性 |
|
塩味 |
塩化ナトリウム |
ミネラルの存在 |
やや低い |
嗜好性 |
|
酸味 |
酒石酸、クエン酸 |
腐敗物や未熟な果実の存在 |
高い |
生体防御 |
|
苦味 |
キニーネ、カフェイン |
アルカロイドの存在 |
高い |
生体防御 |
|
うま味 |
グルタミン酸、イノシン酸 |
タンパク質の存在 |
やや低い |
嗜好性 |
私たちは、普段何気なく食物を口にして味わっていますが、脳は無意識的に、味覚からこれらの情報を読み取っているのです。「おいしい」と感じる食物に共通していることは、その食物の栄養素が、生命を維持するのにプラスになっていることです。これはとてもよくできたシステムで、人は「おいしい」と感じれば、その食物を本能的に摂取し続けます。逆に苦味などを感じると、脳は本能的に「毒」の存在を予知し、私たちに「まずい」と感じさせ、食物の摂取を中止させるのです。これが意味することは、「脳は体に良いものを本能的に知っている」ということです。栄養学の概念がない動物なども、味覚から情報を読み取り、本能で体に良いものを選択的に食べているのです。
「カフェテリア実験」という、実験対象の動物に好きな食物や飲料を選択できる状態にしておき、動物がどのような食物や飲料を選択的に摂取するのかを観察する実験があります。この実験をラットで行ったところ、短期的には食物や飲料の選択には偏りが生じ、摂取した栄養素の量は離散的でしたが、長期的には栄養素の偏りはなくなりました。つまり、ラットは不足している栄養素を含む食品や飲料を、選択して摂取していたのです。この選択的摂取は、あらゆる動物において広く見られます。例えば、カルシウムCaが不足しているニワトリは、カルシウムCaを多く含む飼料を選択的に摂取します。リンPが欠乏しているヒツジは、なんと仲間の毛を食べることさえあるといいます。東洋医学には、「医食同源」という言葉があります。まさに、食べることは病気を予防し、治療することにもなるのです。

図.16 飽食の現代は、いわば巨大なカフェテリア実験が行われているといえる
ただし、科学が発達している現代では、本能に頼らなくても、私たちは体に良い食べ物を選択的に摂取することができます。例えば、青汁などは苦味があって、本能的には「苦味=毒」を予知させますが、ビタミンやミネラルが豊富なことを知識で理解しているので、私たちは「おいしい」と思うことができるのです。よく小さな子供は野菜を嫌いますが、これは「野菜は体に良いのだ」ということを、知識で知らないからです。確かにビタミンやミネラルは体に必要な栄養素ですが、野菜を食べなくても、他の食物からある程度は摂取できる栄養素なので、本能的には「おいしい」と感じにくいのだと思われます。大人になってから野菜が食べられるようになる人がいますが、これは「野菜は体に良いのだ」ということを、知識で理解するようになったからです。したがって、野菜嫌いの子供には、「野菜は体に良いのだ」ということを理解させれば、野菜を食べられるようになるかもしれません。

図.17 青汁は苦味があって、「アルカロイド」などの毒物を連想させる
しかしながら、知識である程度、体に良い食物を見分けられるようになったからといって、私たちは、本能の感覚を失うわけではありません。体の調子が良いとか悪いとか、そのときの気分の良し悪しによって、味の感じ方は異なり、同じ食べ物でも、「おいしい」と感じるときと、「おいしくない」と感じるときがあります。味覚は、体が求めているものに応じて変化し、嗜好性を高めたり、感受性を低下させたりすることによって、摂取を促します。
例えば、長時間運動して、肉体的疲労感を感じたときは、甘いものがいつもより「おいしく」感じられます。これは、体に必要なエネルギーを補給する必要があるため、エネルギー源である「糖質」を積極的に摂取できるように、味覚が調節されている状態です。極度に空腹を感じたときに、大抵のものが「おいしく」感じられるのも、これと同じ理由でしょう。また、普段は強い酸味が苦手であっても、疲労状態では、清涼飲料水や柑橘類の酸味が「おいしく」感じられます。これも、エネルギー代謝を活性化するための「有機酸」を積極的に摂取できるように、一時的に感受性を低下させることによって、味覚が調節されている状態です。このように、基本的には体に良いものは、「おいしい」と感じるようになっているのです。それでは、一体どのような味覚が、最も本能的に「おいしい」と感じるのでしょうか?
味覚の中で、最も強く本能に「おいしい」と感じさせる味覚は、実は「甘味」です。これを意外に思う人は多いかもしれません。しかし、甘味は「糖」の存在を予知させる味覚です。糖は、栄養でいうと「炭水化物」になりますが、炭水化物は、動物の主要な「エネルギー源」です。特に脳では、大半のエネルギー源を「グルコース(ブドウ糖)」に依存しているので、糖は動物にとって、最も重要なエネルギー源と言っても過言ではありません。「甘いものが嫌い」という人ももちろんいると思いますが、糖はご飯や麺などの穀物にも含まれているので、これらのものまで全て嫌いだという人は、ほとんどいないのではないでしょうか。ご飯や麺などに含まれる「デンプン」には、甘味がありませんが、これを分解していくことで生成する「マルトース」や「グルコース」には、強い甘味があります。
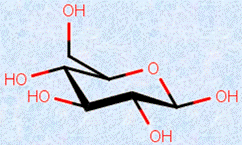
図.18 グルコースの構造式
このように、甘味は本能的に「おいしい」と感じる味覚なのですが、この甘味が「おいしい」と感じる理由には、実は大きな生理学的要因があります。人は、甘いものを食べて甘味を感じると、脳の中で「β -エンドルフィン」などの麻薬様物質が分泌されることが分かっています。このβ -エンドルフィンは、脳内で「麻薬」のように働きかけ、報酬系に作用して、多幸感を生じさせるのです。このように強く報酬系に作用するのは、味覚の中では甘味だけであり、このために甘味は、特殊な味覚となっているということができます。
「砂糖依存症」という、砂糖などの甘味料を多く含む甘い飲料や食品の過剰摂取がやめられなくなる病気がありますが、これはまさに、糖が「麻薬」であることを証明しているものです。砂糖を過度に摂りすぎると、「ドラッグ」のように依存を形成してしまうのです。糖は、人にとって大切なエネルギー源ですが、砂糖などの摂りすぎは、「糖尿病」や「心臓病」の原因になる場合すらあります。甘い食物は、ほどほどにしましょう。

図.19 砂糖の過剰摂取によって、「砂糖依存症」になることもある
また、味覚ではないものの、糖と同じように「脂肪」が、脳内の報酬系に作用することが分かっています。一説によると、脂肪に含まれる脂肪酸の一種である「アラキドン酸」は、体内で変化して、「アナンダミド」という快感などに関係する神経伝達物質に変わります。アナンダミドの名は、「歓喜」を意味するサンスクリット語「アナンダ」から来ています。どうやら、この化合物が脳内の報酬系に作用するらしいのです。さらに、脂肪と糖を同時に摂ると、極端に依存性が高くなり、それぞれ片方だけを摂るよりも、遥かに大きな影響が報酬系に生じることが分かっています。
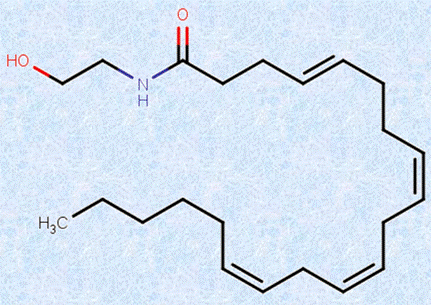
図.20 「アナンダミド」は、快感などに関係する脳内麻薬の一種であると考えられている
脂肪は、栄養でいうと「脂質」のことで、三大栄養素の中では、最も高カロリーな栄養素です。文明が発達した今でこそ、人は飢えで死ぬことはなくなりました。しかし、人類史のほとんどの期間、人は飢えとの戦いでした。人類の歴史のうち200万年は「旧石器時代」であり、この時代ではカロリーの高い食べ物はごく稀で、飢えている状態が、普通の状態だったのです。そこで、進化の過程で人間の体は、飢えに対して強くなるように適応してきました。つまり、食べ物が少なくて餓死する人が多かったから、飢えに対する抵抗力を持つために、高カロリーの脂肪を体に蓄積させるようになった訳です。いつも食べ物があるとは限らないので、食べたものが脂肪として体にたくさん残った人の方が、食べ物が乏しくなったときに生き延びる可能性が高くなります。カロリーの高い食べ物を「おいしい」と思う本能は、私たちの遺伝子に刻み込まれています。今日、私たちの家の冷蔵庫には、カロリーの高い食べ物があふれているかもしれませんが、DNAは私たちが依然として旧石器時代のサバンナにいると思っているのです。
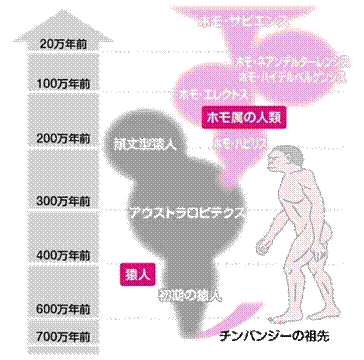
図.21 ホモ属の人類は今から200万年前に誕生した
実際に、私たちの体の中で空腹時に働く血糖値を上げるホルモンは、「グルカゴン」や「アドレナリン」などたくさんありますが、満腹時に働く血糖値を下げるホルモンは、膵臓から分泌される「インスリン」の1つだけなのです。したがって、高カロリーである脂肪を摂取することは、人を含めすべての動物にとって、飢えをしのぐために重要なことだったのです。だから、脂肪を多く含むラーメンなどの食物を食べると、「おいしい」と感じるのです。また、「マヨラー」と呼ばれるマヨネーズが大好きな人たちがいますが、これは、マヨネーズに多量含まれている油に依存している可能性が高いです。
現代は飽食の時代となり、食べるのに困ることはほとんどなくなりました。そうすると、それが過剰の脂肪となり、遂には糖尿病や痛風、高血圧などの生活習慣病を引き起こす原因にもなっています。かつては、環境に適応して有利だった資質が、この現代社会においては、逆に不利に働いています。つまり、肥満という現象は、人類が何万年、何十万年をかけて進化させ適応させ最適化させてきた体が、ここ数百年の人類社会の劇的な変化に付いていけていないことの現れなのです。
・参考文献
1) 大宮信光「面白いほどよくわかる化学」日本文芸社(2003年発行)
2) 都甲潔/飯山悟 共著「トコトン追究 食品・料理・味覚の科学」講談社(2011年発行)
3) 西村敏英/江草愛 共著『食べ物の「コク」を科学する』日本農芸化学会 化学と生物54(2):102-108(2016)
4) 日本化学会編「身近な現象の化学 PART-2 台所の化学」倍風館(1989年発行)
5) 船山信次「こわくない有機化合物超入門」技術評論社(2014年発行)
6) 前橋健二「甘味の基礎知識」日本醸造協会誌106(12),818-825,2011-12-15
7) 村田容常「焼いたスイーツとメイラード反応」化学と教育67巻2号(2019年)
8) Yuval Noah Harari 著/柴田裕之 訳「サピエンス全史(上)―文明の構造と人類の幸福」河出書房新社(2016年発行)